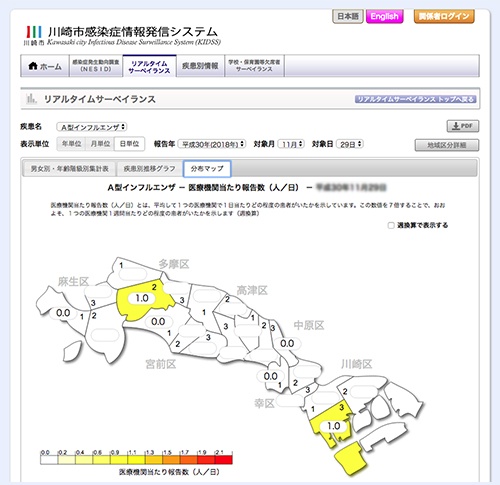そのときには臨床医というお立場で呼ばれたのですね。
ふだんの臨床では、患者さんをよく見て検査をして、その結果をもとに治療をしていくわけですが、そういう手段のないようなところでは、たとえば呼吸数や肋間のへこみ具合から重症かどうかを判断して、必要に応じて入院治療ができる医療機関に送ります。そういう方法を医療の行き届かない地域で実践できるようにすることが中心で、日本での医療との違いが強烈に印象に残りました。
それと、私が勤めていた国立小児病院の感染科では、アジアなどからの研修生を受け入れ始めていたんですね。あるとき、フィリピンから来た若い小児科医から「ここには感染症はいない。本当の感染症をみたいならあなたがアジアに来たほうがいい」と言われました。たしかに国立小児病院には、真の感染症が入院してくるようなことはなく、彼らが現場で診ている感染症は教科書でしか知りませんでした。
この2つのことが心に残っていた矢先に、WPROで、予防接種と感染症に精通し、臨床経験も研究経験もある日本人を探しているということで、声をかけてもらったのです。
WPROのあるマニラに行かれたのが何歳のときですか?
40歳を過ぎた頃ですね。71年卒業で90年にWPROに行ったので、20年近く臨床経験を積んでからです。そのままWHOにいようかという気持ちもあったものの、いろいろな事情で4年後に母校に戻り、2年ほど分院で小児科の責任者を務めました。
そして、当時の国立予防衛生研究所が改組して「国立感染症研究所」をつくる際、「感染症情報センター」の立ち上げにあたって、感染症のサーベイランスと病気の説明ができる、感染症のラボ経験のある臨床医がほしいということで誘われました。それが大きな転機でしたね。